⭐ tripleS「Girls Never Die」
韓国の24人組女性アイドルグループ「tripleS」のアルバム「ASSEMBLE24」のタイトル曲「Girls Never Die」。2年弱かけてメンバーを公開していき、ついに完全体の24人でアルバムをリリースした。
曲や MV を視聴して感じたのは、AKB48 の再解釈であり続編のようだということ。人数が多いため AKB48 を連想したのもあるかもしれないが、それ以上に曲や MV から感じた。MV の色味や曲の雰囲気が影響しているのか、見始めてすぐに「RIVER」を思い出した。「RIVER」では AKB48 が「私たちだってできる」というメッセージを発しているが、この「Girls Never Die」では最初に「もう一度やってみよう」というセリフから始まる。自分もできるという宣言と共に 00-10年代でカルチャーの中心に躍り出た AKB、かつての勢いを無くした今、強引な解釈かもしれないが、tripleS があのムーブメントをもう一度行う、つまり、再解釈であり続編のようだと感じた。
MVも非常にかっこいい。外の世界ではなくビルの一室で独自の世界を作る女の子たち。交通事故や浴槽に潜るなど、死をほのめかすシーンがありながら、最終的には(しばしば物語などでは死の象徴として描かれる)カラスが空に飛び立つシーンで終わる。そして、曲のタイトルが「Girls Never Die」なのだ。
少し前に、tripleS に本田仁美が加入するのではないかという噂が立ったが、もし AKB48 が本田仁美センターでこの曲をやったらどうだっただろうか、と考えてしまった。
by grandcolline
🎫 SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2024

渋谷ストリームで映画を上映するというイベント。職場が近くにあるのでたまたまその場を通りかかった時にこのイベントを知り、土曜日に「ニュー・シネマ・パラダイス」を観にいってみた。
感想としては、野外スクリーンで「ニュー・シネマ・パラダイス」を観るという体験は生涯で一度はしておいた方がいい。マジでおすすめ。家でのスマホ視聴や、通常の映画館では味わえない体験だった。特に、アルフレードが広場の壁に映画を映し出すシーンは、街中で映画を見ている自分たちと重なり、映画の一部になったようなんとも言えない感動的な気持ちになった。
自分自身が渋谷の騒音の中で観たこともあり、映画中の戦後イタリアの観客たちが騒ぎながら映画を観ているシーンが特に印象的だった。近年、映画上映時のマナーについて不満を述べる SNS 投稿を見かけることが多いと感じている。上映中の会話やスマホ使用などの話。自分の大部分はこの不満に賛同的だが、一方でもっと自由でいいんじゃないかと思う自分もいる訳で、そんな自分は「ニュー・シネマ・パラダイス」で騒いで映画を観ている観客たちがとても愛おしく感じた。
結局これは TPO に関する話だと思っていて、映画館では静かに観た方がいいが、もっと自由にみんなで映画を観る場所があったらいいんじゃないかと思った。そういう意味でも、この「SHIBUYA STREAM THEATER WEEK 2024」は良かった。隣の人と喋ってもいいし、スマホを見てもいい、途中で帰ってもいい。そういう映画体験ができる場所やイベントがもっと増えたらいいなと思う。

あと、クラフトビールおいしかった 🍺
by grandcolline
🎞️ 濱口竜介「悪は存在しない」
「ドライブ・マイ・カー」の濱口竜介監督の最新作。音楽も同映画で音楽を担当した石橋英子。この映画が石橋英子がライブパフォーマンスのための映像を濱口監督に依頼したことをきっかけという面白いもの。奇奇怪怪で紹介されてた「Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下」で鑑賞。文化村なので道玄坂上かと思っていたら、全然場所が違った。ちゃんと調べてから行きましょう(教訓)
正直な感想を言うと「抽象度が高すぎじゃない? うん、これはなかなか意味がわからないぞ」と笑。ただ、見るのがつらいということはなく、美しい自然の映像と音楽、物語途中で挟まる面白い会話劇などで、映画自体は全く飽きることがなく楽しめる。
主人公の巧は人間の社会や秩序によるコントロールの外側にいるような気がした。何でも屋という職業、花のお迎えを忘れるなど。とはいえ、自由気ままに生きているわけでなく、外部からの作用がない自分自身のルーティーンで生活を送っている。そんな彼は「自然とのバランスが大事」ということを訴える。そういったところから、人間の文明と自然のバランスをとるバランサーであり、番人なのではないかと考えた。
また、物語全編を通して「鹿」と「水」が象徴的に描かれている。映画を見ている最中は、鹿を自然の抽象化という解釈で『自然 = 鹿 <--> 巧 <--> 人間』という関係性を考えていたが、ラストシーンまで観て今思うと、巧と鹿はもっと同義で『自然 = 水 <--> 鹿 = 巧 <--> 人間』という関係性なんじゃないかと考えている。「巧の水くみ」と「鹿の水飲み場」がともに丁寧に描かれているところに、巧と鹿の同一性みたいな解釈もできるかなと。そうすると、花を「自然に対する人間の純粋な好奇心の象徴」(つまり、人間の文明のもっともピュアな部分のメタファー)としてとらえても面白いなと。巧がおもりをしている点も踏まえて。
そんなことをあれこれ考えては見たものの、結局「なーんもわからん!でも面白い!」につきる。大学時代にゴダールをたくさん見てた時期があったが、ゴダールっぽさを感じるショットも多く、そこも好きでした。名作!
by grandcolline
📖 三宅香帆「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」
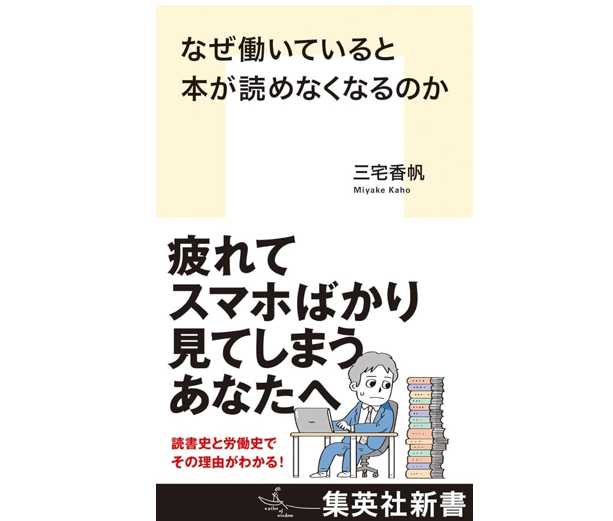
「三宅香帆」の新書「なぜ働いていると本が読めなくなるのか」。X で下記のポストを見かけて、自分も「花束みたいな恋をした」には思うことがいろいろあったので、気になって購入。品切れの本屋も多かったらしく、新宿に行ったついでにたまたま寄った紀伊國屋では在庫があってよかった。
前半は明治時代から現代までの生活と読書についての歴史的な説明。ここだけ読むとタイトルとは関係ない日本人の読書史の話である。ただ、読み進めると、現代の話になっていき、情報と読書の違いの話になる。そこで語られるのは、情報はノイズがなく、読書はノイズがあるという内容。ノイズがあることで、受動的な知識を得られることが読書の良さだという。ここで、前半の歴史の説明はまさにノイズだったのだなと気づく訳である。すごい伏線でカタルシスすら感じた。
by grandcolline

